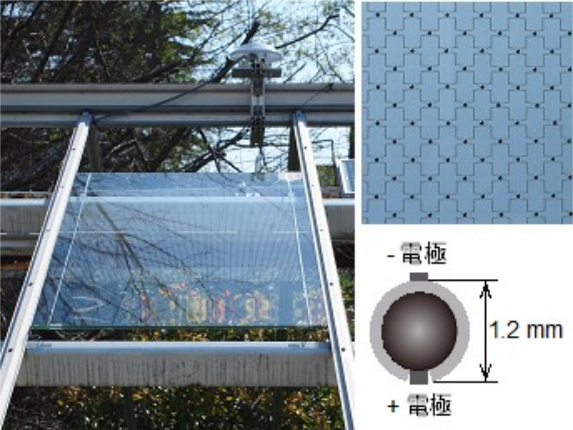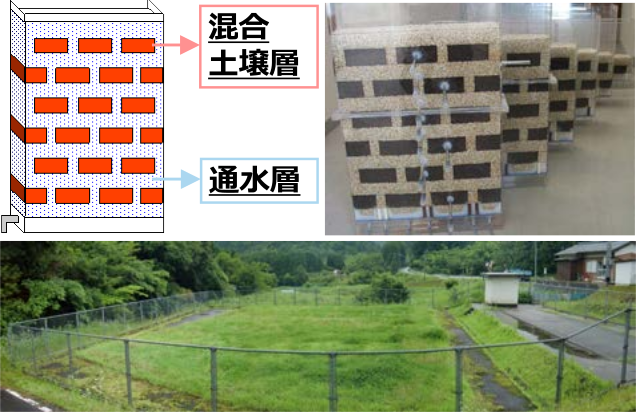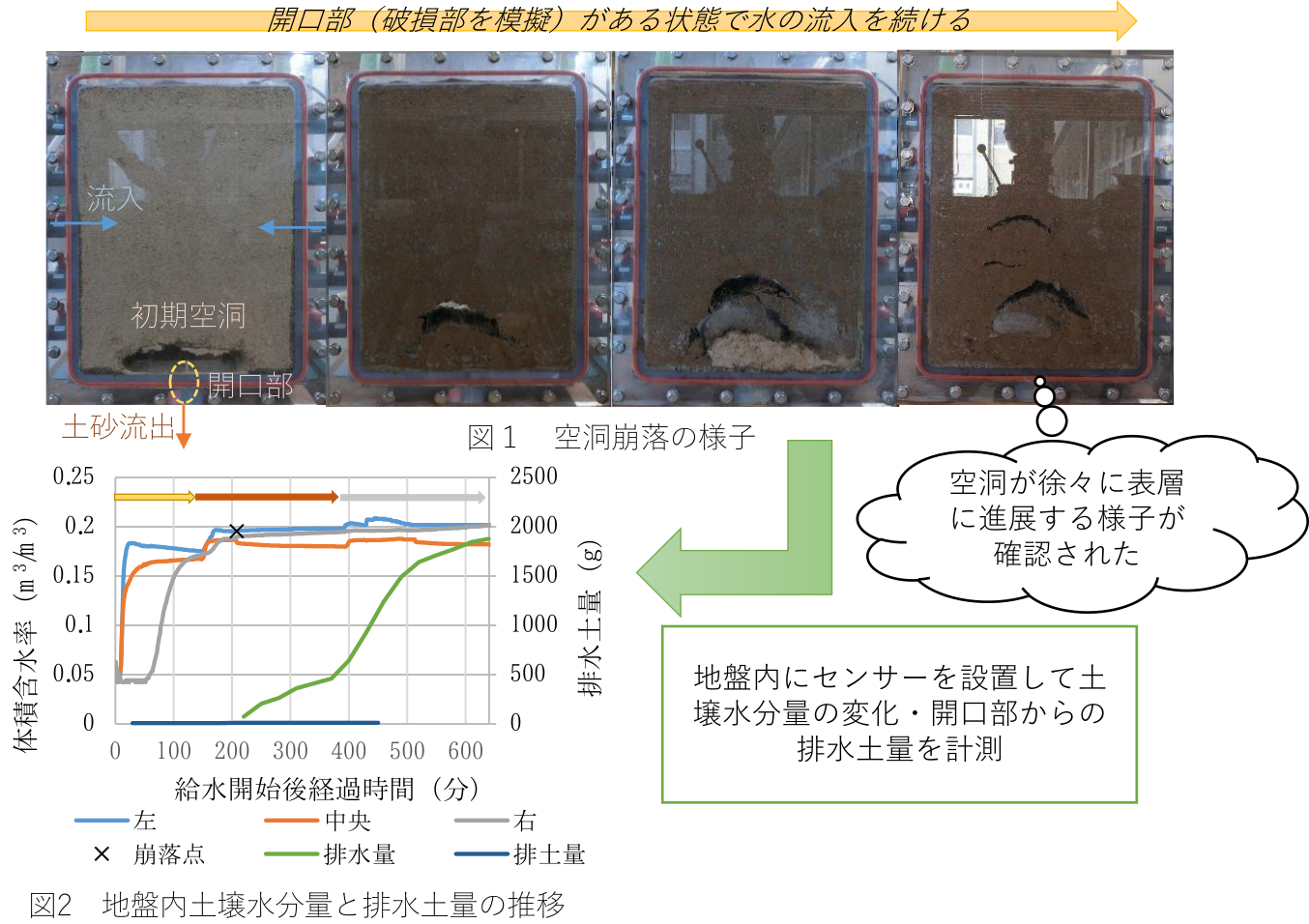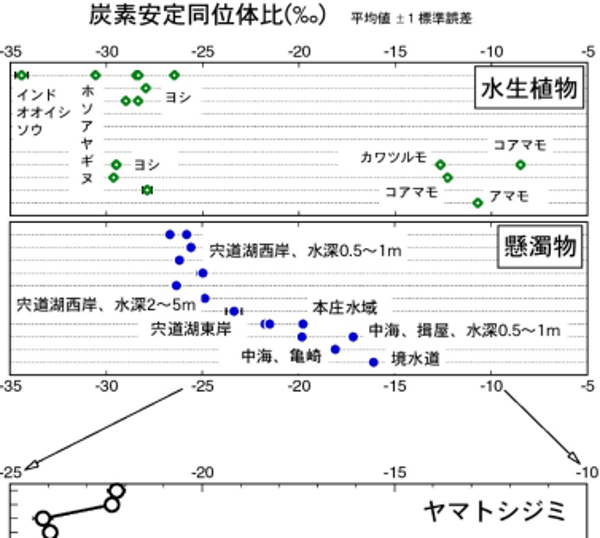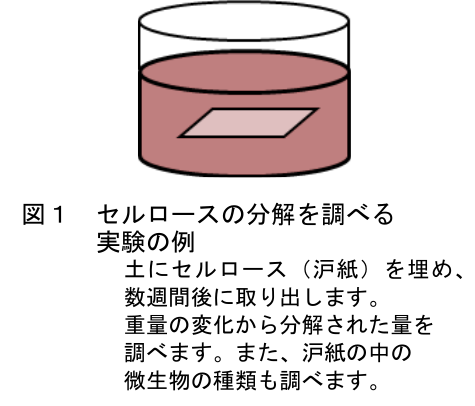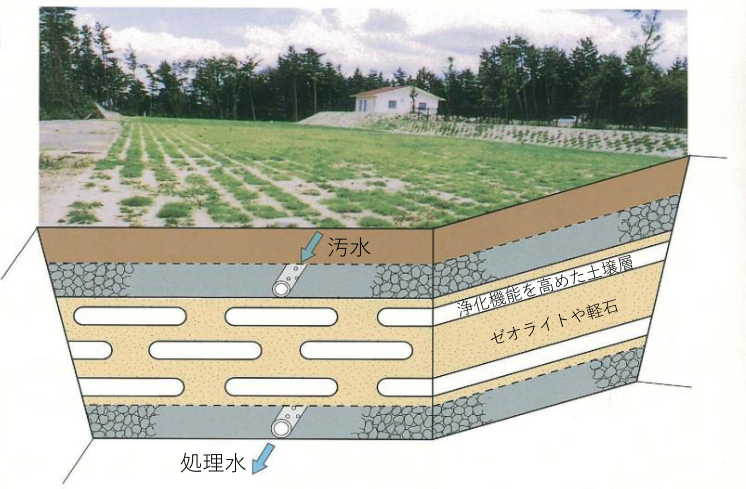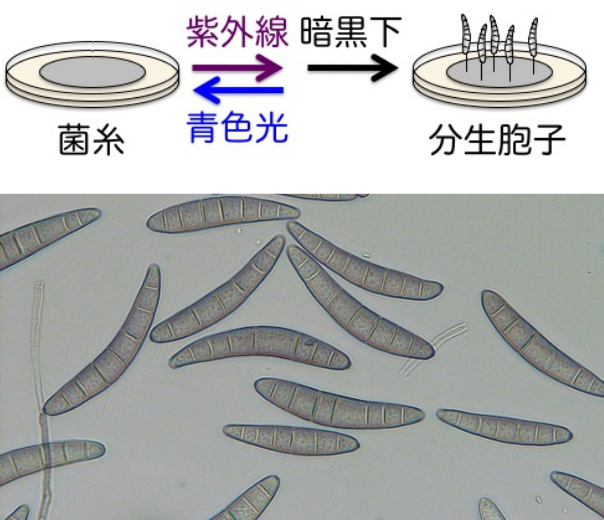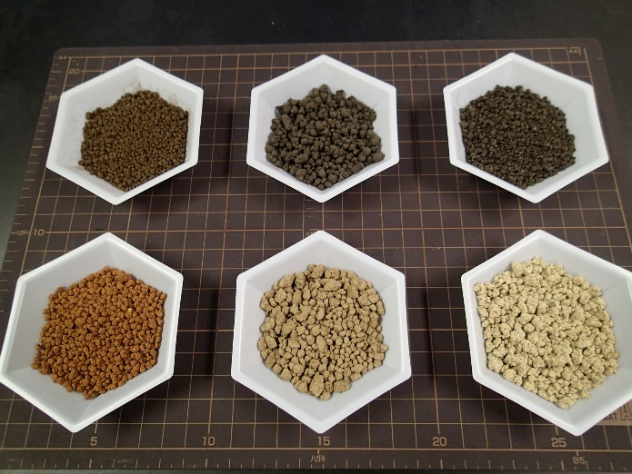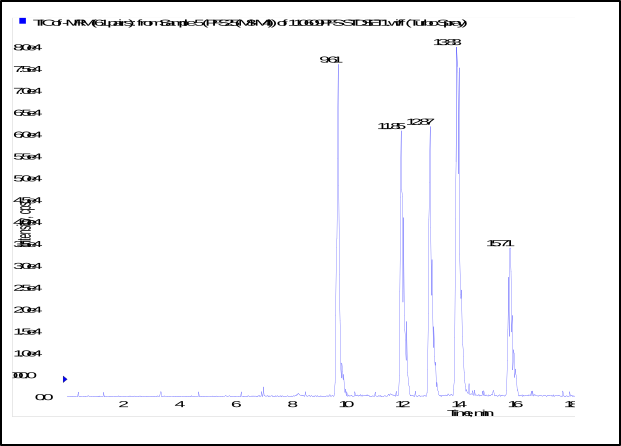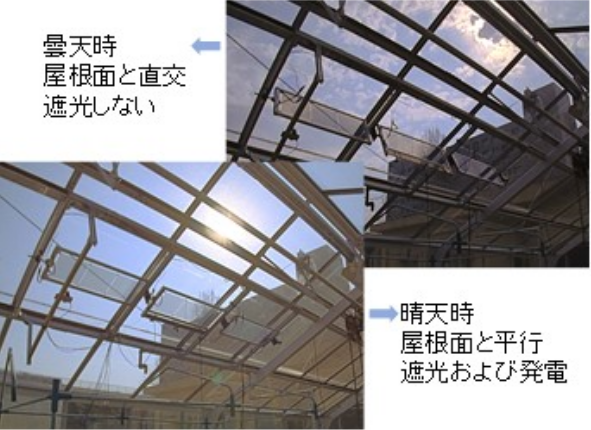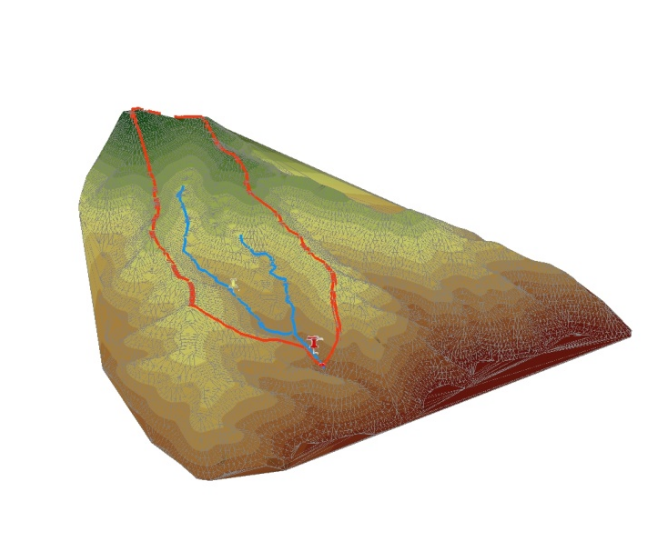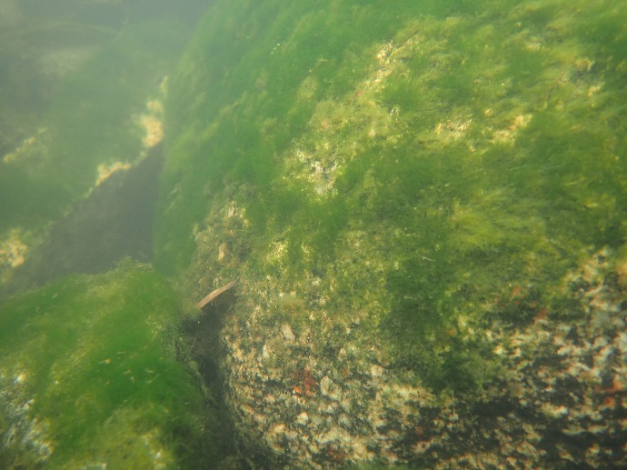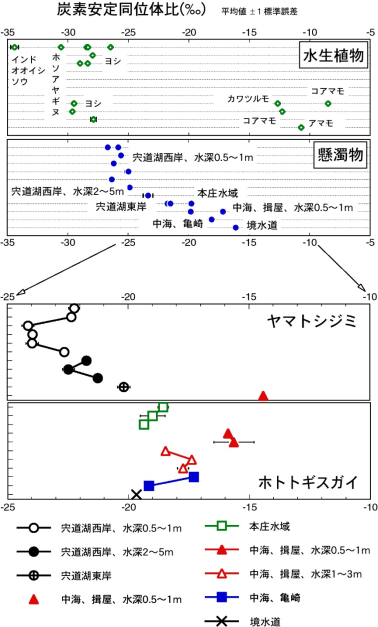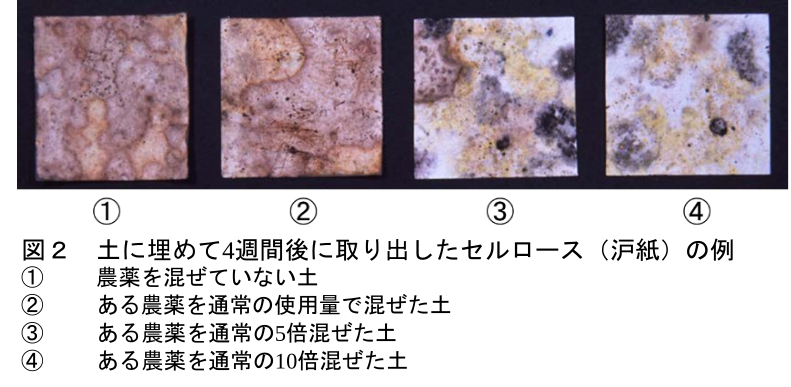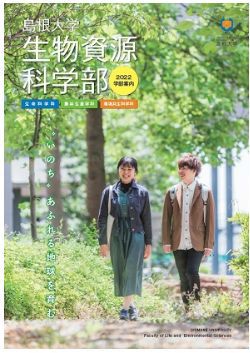本学の地(知)の利を生かし、斐伊川流域や三瓶山で野外実習を行います。ここには、森林、土壌、汽水域といった生態系サービス(自然の恵み)、農地や地域資源の保全と持続的利用、河川構造物や水処理施設といった要素が揃っており、環境共生型社会を構築する対象地域として絶好のフィールドです。野外調査に加えて大学キャンパス内でも様々な実習を行います。 Read More
Research X SDGs
What kind of researches we have.
 food resources
安全な食料を生産し、飢餓をなくす
food resources
安全な食料を生産し、飢餓をなくす
![]()
![]()
 safe water
いのちに必要な水
safe water
いのちに必要な水
![]()
![]()
 energy and life
エネルギーと生活
energy and life
エネルギーと生活
![]()
![]()
![]()
![]()
 climate change
気候変動に具体的な対策を
climate change
気候変動に具体的な対策を
![]()
 sea, river, lake
海、川、湖の環境を守る
sea, river, lake
海、川、湖の環境を守る
![]()
 forest and plain
森林と平野
forest and plain
森林と平野
![]()